- (1) Future BASIC II日本語版
- (2) True BASIC
- (3) Chipmunk BASIC
- (4) METAL
- (5) Cross BASIC
- (6) Quick BASIC
- (7) SC Basic
- (8) BWBASIC
- (9) VIP BASIC
- (2) True BASIC
- ●:互換性があり手直しの必要はほとんどない
- ▲:同類の命令があるが、命令が異なる
- 無印:移植が難しい命令、または不可能な命令
- ▲:同類の命令があるが、命令が異なる
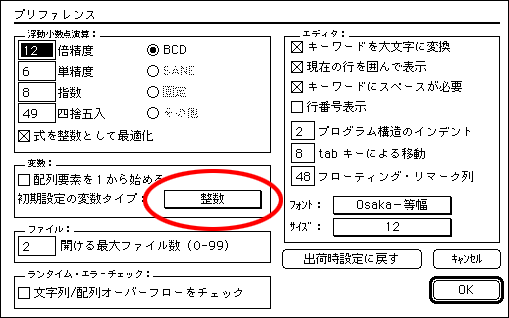
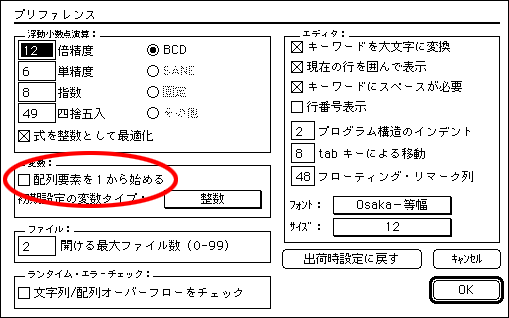
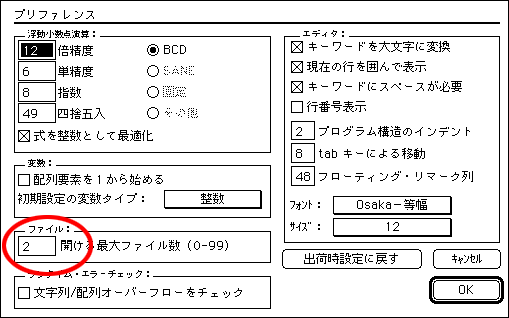
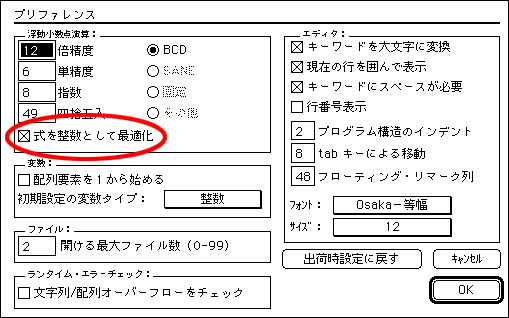
- ・単音のみ(PC-9801など一定の高さの音)
- BEEP文そのままで変更する必要はありません。
- ・単音のみ(MZ-700など音程を変化させる事ができるもの)
- 音程を変化させる事ができる機種は多くあります。これらはBEEP音は、そのままで変更する必要はありません。音程を変化させる部分は「SOUND」命令を使って下さい。
- ・MML (Music Macro Language)を使用しているもの
- 単音のものであればFuture BASIC上で独自の解析関数を作成し処理することが可能です。
- ・PSG (FM-7/MZ-1500)
- PSG (Programmable Sound Generator)を使用している場合、3重和音または6重和音まで演奏させる事が出来ます。MMLと組み合わせて処理されるためFuture BASICでは独自に関数を用意する必要があります。また、サウンドリソースと併用して処理を行う必要があり、かなり困難です。
- ・FM音源 (PC-8801mkSR/MZ-2500)
- FM音源(OPN/OPM)を使用しているものは、ほぼ移植不可能です。素直にあきらめましょう。
- ・Music Track (X1turboZ/X68000)
- 音楽等のトラックバッファを確保しMMLで演奏するためFuture BASICへの移植は実質的に不可能な状態です。
- ・PCM / ADPCM (X68000)
- PCMはサンプリングしたものを出力します。これはMacintosh上での標準的なサウンド出力形態ですので、サウンドデータさえあれば「SOUND リソース名」で手軽に移植できます。
- ・座標系の違い
- 一般のBASICと異なりMacintoshのグラフィック座標は「数学座標」です。例えば座標(0,0)から(0,0)に線を表示する場合、以下のようになります。
- *一般のBASICでは点が1ドット表示される
- *Future BASICでは何も表示されない
- このためグラフィックを扱っているプログラムの場合、水平線、垂直線が表示されません。このような場合は、全て座標の変更が必要になります。例えば(0,0)から(319,199)まで線を引く場合
- *一般のBASIC:LINE (0,0)-(319,199)
- *Future BASIC:PLOT 0,0 TO 320,200
- となります。
- *一般のBASICでは点が1ドット表示される
- ・命令の違い
- 一般のBASICとFuture BASICではグラフィックに関係する命令が異なります。以下のように変更する必要があります。(左側は従来のBASIC、右側がFuture BASIC)
点を表示 PSET(x,y) PLOT x,y TO x+1,y+1 点を消去 PRESET(x,y) PLOT x,y TO x+1,y+1(あらかじめCOLOR命令で背景色を指定する) 線を描画 LINE(x1,y1)-(x2,y2) PLOT x1,y1 TO x2+1,y2+1 円を描画 CIRCLE(x,y),r CIRCLE(x,y),r 多角形を描画 POLY 独自に関数を作成する必要あり(QuickDrawの命令を組み合わせて使用する) パターン描画 PATTERN 独自に関数を作成する必要あり(QuickDrawの命令を組み合わせて使用する) シンボル文字 SYMBOL TEXT命令とCALL MOVETO(x,y)とPRINT命令を組み合わせる 塗りつぶし(境界色指定) PAINT 独自に関数を作成する必要あり(QuickDrawの命令を組み合わせて使用する) 塗りつぶし(単色指定) PAINT 独自に関数を作成する必要あり(QuickDrawの命令を組み合わせて使用する) 画面消去 CLS CLS ボックス LINE(x1,y1)-(x2,y2),B BOX x1,y1 TO x2+1,y2+1 ボックス(フィル) LINE(x1,y1)-(x2,y2),BF BOX FILL x1,y1 TO x2+1,y2+1 グラフィック取り込み GET@ USR GETPICT グラフィック表示 PUT@ PICTURE グラフィック画面読み込み GLOAD 独自に関数を作成する必要あり グラフィック画面保存 GSAVE 独自に関数を作成する必要あり ビューポート指定 VIEW クリッピングリージョンを指定(QuickDrawの命令を組み合わせて使用する) ウィンドウサイズ WINDOW WINDOW命令で指定 画面解像度 SCREEN/INIT 独自に関数を作成する必要あり 色数指定 SCREEN/INIT 独自に関数を作成する必要あり(STAZ Softwareのサイトにサンプルあり) スクロール ROLL SCROLL 連続直線 LINE/CONNECT PLOT x1,y1 TO x2,y2 TO x3,y3 TO... パターン描画位置指定 POSITION x,y CALL MOVETO(x,y) 点の色を読み出す POINT(x,y) POINT x,y (ただし、白黒の値しか返さない) パレット COLOR= 独自に関数を作成する必要あり(QuickDrawの命令を組み合わせて使用する)
| 0(黒色) | _zBlack | |
| 1(青色) | _zBlue | |
| 2(赤色) | _zRed | |
| 3(紫色) | _zMagenta | |
| 4(緑色) | _zGreen | |
| 5(水色) | _zCyan | |
| 6(黄色) | _zYellow | |
| 7(白色) | _zWhite |